「なんでこんなに勉強してるのに、全然覚えられないんだろう…」
「頑張ってるのに、テストの点数に反映されない…」
こんなモヤモヤを感じたことはありませんか? 真面目に取り組んでいるのに成果が出ないのは、努力の方向がズレているだけかもしれません。
「どうせ才能のある人には敵わない」と諦めていた僕が、あるとき出会った1冊の本で、考えが180度変わりました。
その本の名前は『科学的根拠に基づく最高の勉強法』(著:安川康介)。
医師国家試験トップ1%というとんでもない結果を出した著者が、科学的に効果が証明された勉強法をわかりやすく解説しています。
この記事では、 a.本書に書かれている“本当に意味のある勉強法”の概要と、 b.それを僕自身や周囲の人が実践してどう変化したか …を具体的にお伝えしていきます。
この記事はこんな方におすすめです:
・受験や資格試験を控えている
・勉強しても記憶に定着せず悩んでいる
・脳科学や心理学に基づいた方法を知りたい
・医者レベルの効率的な勉強法に興味がある
科学的根拠に基づく最高の勉強法amzn.to1,760円(2025年03月28日 16:30時点 詳しくはこちら)Amazon.co.jpで購入する
今だと、Audible版だと99円で購入できるのでおすすめです。
なぜ「科学的な勉強法」が必要なのか?
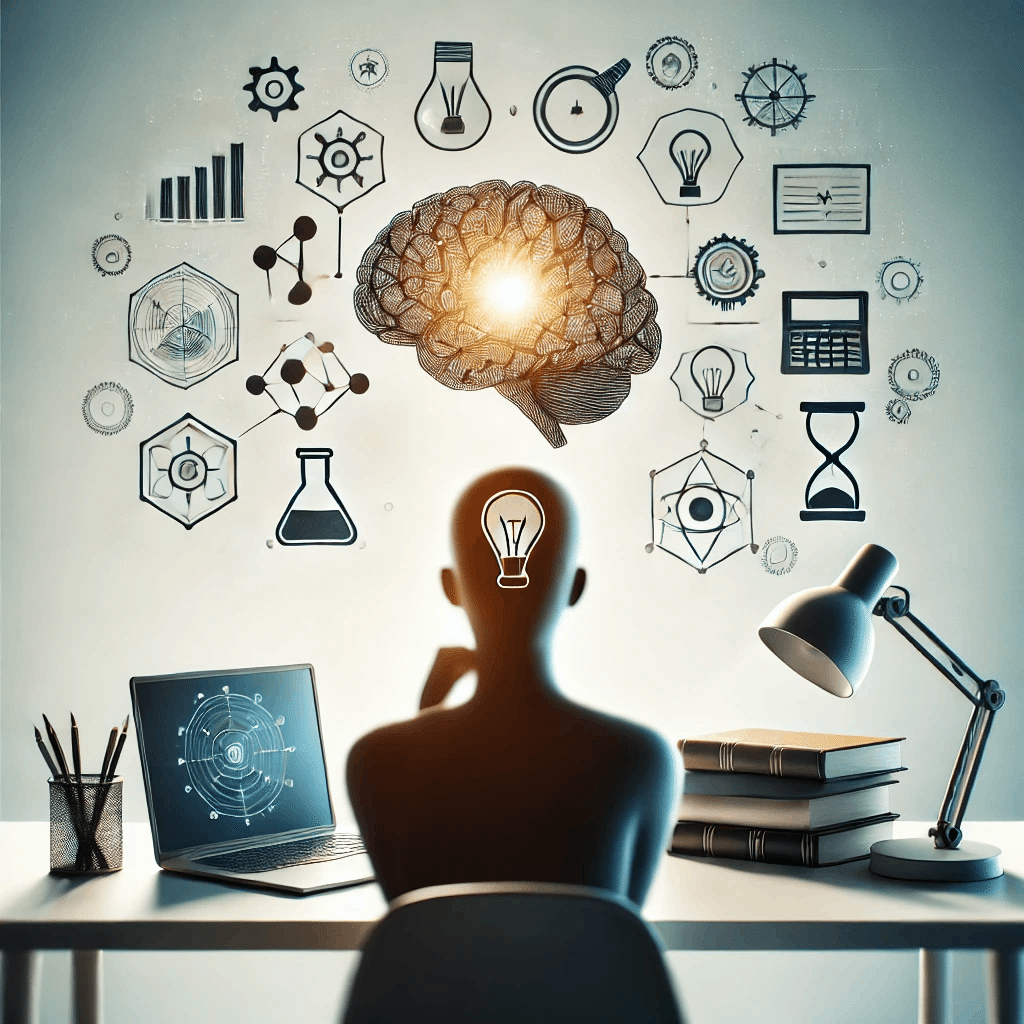
頑張って勉強しているのに成績が伸びない。
これは多くの人にとって、非常に共通する悩みです。 でも実は、その原因は「才能の差」ではなく、「やり方の差」にある可能性が高いのです。
たとえば、こんな勉強法をしていませんか?
・教科書を何度も読み返す
・ノートをきれいにまとめる
・単語帳を眺めながら覚える
これらはいかにも「勉強している感」はあるものの、実際のところ、脳にとっては“楽すぎる”行為です。
心理学や脳科学の研究では、こうした“受動的な学習”は、記憶への定着率が非常に低いことがわかっています。
つまり、「努力してるのに成果が出ない」と感じるのは、あなたの脳がラクをしているから。
逆に、ちょっとしんどいと感じる“能動的な学習”こそが、記憶を強化し、理解を深めてくれるのです。
「じゃあ、どんな勉強法が脳に効果的なのか?」
それこそが本書のテーマです。
安川氏が紹介するのは、数々の研究によって裏付けられた“科学的に正しい学習法”。
つまり、感覚や根性に頼らず、脳の特性を踏まえて「どうすれば最も効率的に覚えられるか」を追求したやり方です。
ここで紹介する方法は、どれも特別な道具も知識も不要。
ただ「やり方を知って、ちょっと工夫する」だけで、誰でも今日から取り入れられます。
必要なのは、才能ではなく、正しい方法を知ること。
この記事では、その具体的な中身を紹介していきます。
本書で紹介されている主な勉強法
『科学的根拠に基づく最高の勉強法』で紹介されているのは、数ある学習法の中でも、特に再現性が高く、かつ実際の成績アップにつながると研究で裏付けられた“王道の3メソッド”です。それが、
アクティブリコール(思い出す練習)
分散学習(間隔をあけた復習)
インターリービング(交互に学ぶ)
これら3つはいずれも「能動的な学習」を促し、脳に“あえて負荷をかける”ことで記憶を強固にし、応用力を養うことが目的です。以下では、それぞれを具体的な例とともに丁寧に解説していきます
アクティブリコール(思い出す力を鍛える)
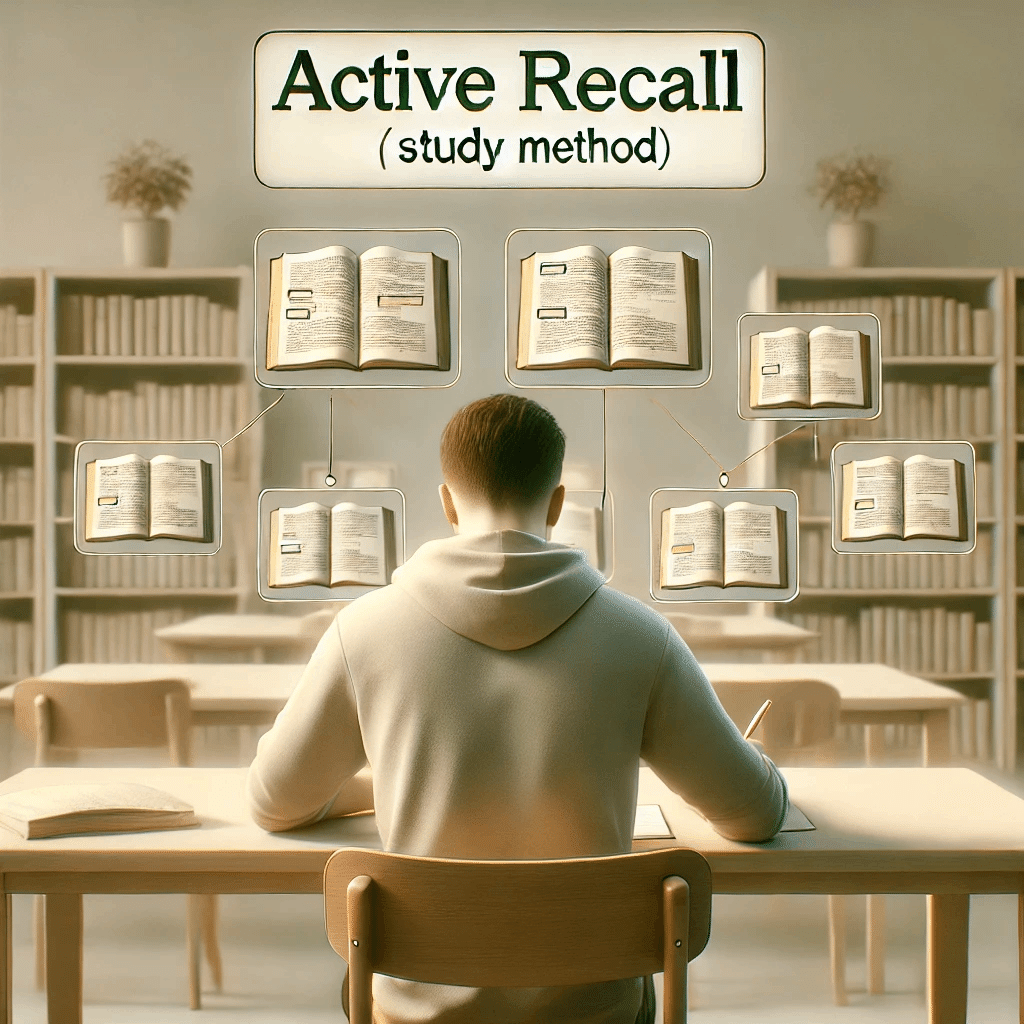
学習 → 記憶を呼び出す練習 → 記憶が深まる
↘ 説明する、書き出す、問題を解く
アクティブリコールとは、“自分の力で思い出す”ことに重きを置いた学習法です。
脳にとって「情報を受け取る」よりも「情報を引き出す」行為の方が何倍も記憶に残りやすいという研究結果があります。
たとえば、次のようなシーンを想像してみてください:
教科書を読んだ後、本を閉じて内容を自分の言葉で要約する
ノートを見ずに、頭の中で図を再現する
友人や家族に「これってこういうことなんだよ」と説明してみる
これらはすべて、脳の“検索モード”をオンにするアクションです。
Googleのように情報を蓄積するだけではなく、「必要なときに引き出せる状態」を作ることこそ、真の理解につながります。
実際、アクティブリコールは多くの医学部生・法科大学院生など、暗記量が膨大な分野でも導入されており、成果を上げています。
特に効果的なのが「セルフテスト」です。
問題を解いたあとに答え合わせをするのではなく、まず自分で答えを想起し、それを紙に書き出してみる。
この“思い出す→確認する”という流れが記憶の回路を強化します。
注意点は、「覚えていない部分を炙り出すことを恐れない」こと。
むしろ、忘れているからこそ、学習価値が高まる瞬間なのです。
分散学習(間隔をあけて覚える)
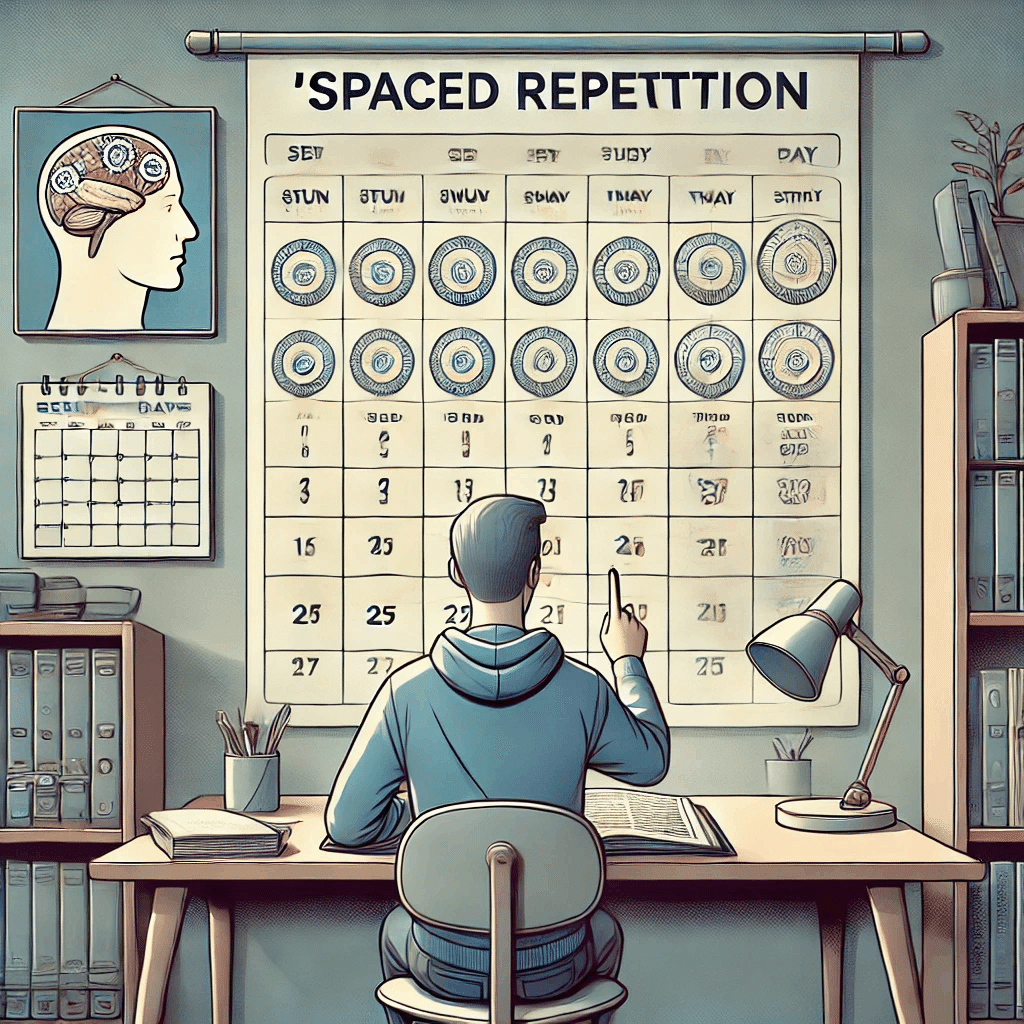
初回学習 → 1日後に復習 → 3日後に復習 → 7日後に復習
↑ ↑ ↑
忘却が始まるタイミングを狙う
次に紹介するのは「分散学習」──これは“まとめて覚える”のではなく、“忘れかけた頃にもう一度触れる”という方法です。
この手法の背景には、「エビングハウスの忘却曲線」という有名な実験があります。人間の記憶は、何もしなければ1日で半分以上を忘れるという性質があります。
しかし、ちょうど忘れかけたタイミングで復習を入れると、その情報は“思い出す努力”を通じて、より深く脳に刻まれるのです。
たとえば、次のようなスケジュールが推奨されます:
1回目の学習(初回)
2回目:翌日
3回目:3日後
4回目:7日後
5回目:2週間後
このように段階的に復習間隔をあけると、脳は「これは繰り返し現れる大事な情報だ」と認識し、長期記憶として保持しようとします。
また、1日10時間勉強しても1日で忘れる内容と、毎日1時間×10日でしっかり定着する内容、どちらが賢いかは明らかです。
この“量よりタイミング”の考え方は、勉強に苦手意識がある人ほど大きな武器になります。
注意点は、「復習の内容を変化させること」。 初回は読んで理解、次回は要点の抜き出し、その次は図解化や口頭説明など、アプローチを変えることで、定着率がさらにアップします。
インターリービング(交互に学ぶ)
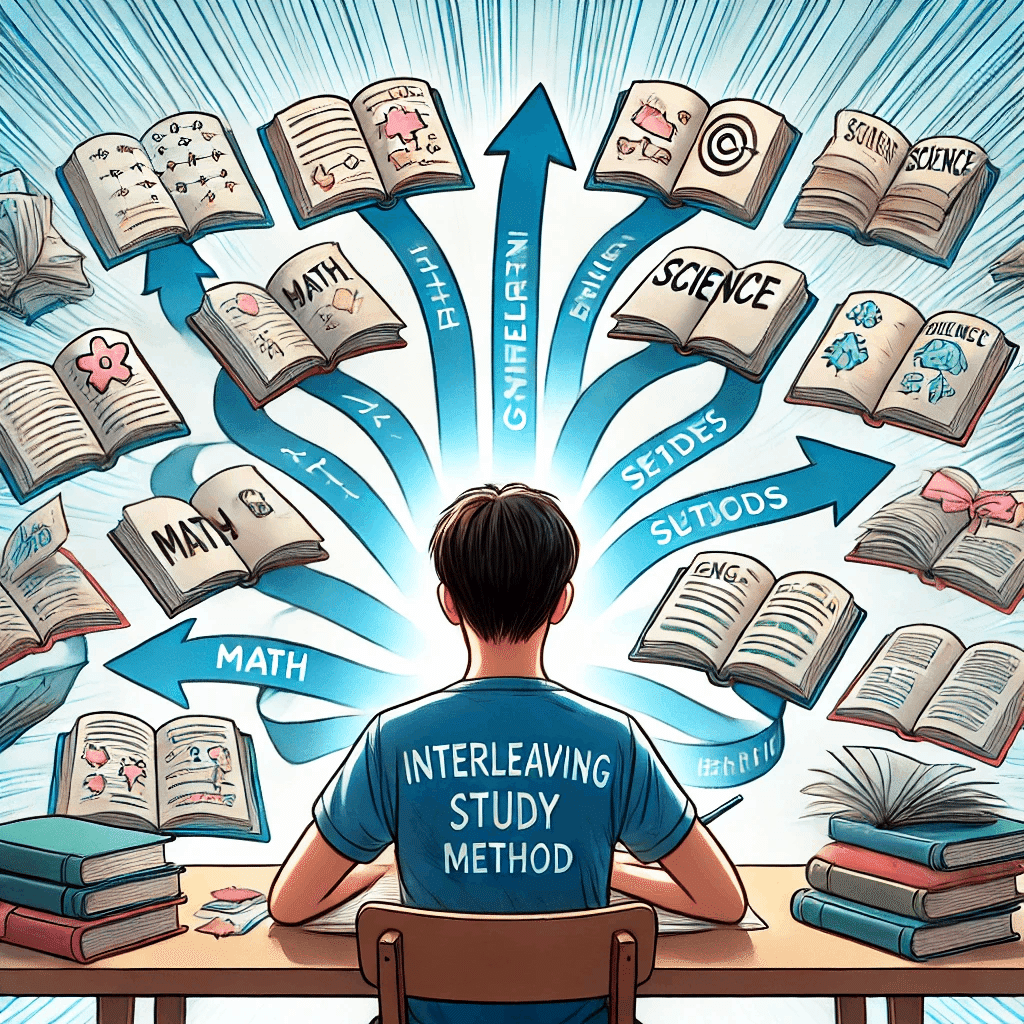
英語 → 数学 → 理科 → 英語 → 社会 → 数学
↘ ↘ ↘ ↘ ↘
脳が混乱 → 情報整理 → 応用力アップ
最後に紹介するのが「インターリービング学習法」。
これは、同じテーマを連続して学ぶのではなく、異なるテーマを“交互”に学ぶことによって、脳の混乱と整理を促進させる方法です。
たとえば、
英単語 → 数学 → 歴史 → 英単語 → 科学 のように、ジャンルを切り替えて学ぶことがポイントです。
「同じ科目で一気に覚えた方が早いんじゃないの?」と思うかもしれません。
実は、この“楽に感じる一気学習”は、短期記憶には残っても長期記憶には定着しにくいという欠点があります。
一方、インターリービングでは「これは何の問題だったっけ?」「どの解き方を使えばいいんだ?」と、毎回思考をリセットさせる必要が出てきます。
この“思考の切り替えコスト”こそが、学習の深度を高めるカギ。
特に応用問題や初見のケースに強くなるという利点があり、単純な暗記型試験だけでなく、論述・プレゼン・実技試験など“総合力”を求められる場面でこそ真価を発揮します。
実践方法としては、
毎日の学習スケジュールに「複数科目」を入れる
同じ科目内でも「テーマ」を切り替える(例:数学なら計算→図形→関数)
問題集の順番をあえてバラバラにして解く
など、意図的に“揺さぶり”を入れることがポイントです。
結果を出すなら、科学に裏付けられた勉強法を
以上、
a. 『科学的根拠に基づく最高の勉強法』に書かれていた3つの勉強法(アクティブリコール/分散学習/インターリービング)をわかりやすく解説しつつ、
b. 実際にその内容を取り入れた実践例や、読者がどのように使えるかのイメージを交えながら紹介してきました。
この記事を読んでくださった方の中には、
・これから受験や資格試験に挑む方
・勉強が苦手で「どうしても覚えられない」と悩んでいる方
・もっと効率よく学びたい社会人の方
など、さまざまな立場の方がいらっしゃると思います。
もし、「そろそろ本気で勉強を変えたい」と思っている方がいれば、
ぜひ今回ご紹介した科学的勉強法の中から、1つでも試してみてください。
ここで紹介した内容は、すべて**研究によって効果が実証されている
“本物の勉強法”です。
そして、実践した人から順に、確実に成果を積み重ねています。
最近では、「わからないことを丁寧に教えてもらう」のが難しくなってきました。
なぜなら、
・学校や職場の先生や上司も忙しくて余裕がない
・何かを教えるには「パワハラ」「時間のムダ」と思われる風潮もある
…そんな背景があるからです。
だからこそ今の時代は、「自分の面倒を自分で見られる人」だけが、圧倒的に伸びていきます。
その第一歩が、「正しい勉強のやり方を、自分で選び、実践すること」です。
もしあなたが、この記事の中で紹介したアクション──
・テキストを閉じて思い出す練習をしてみる
・今日の復習を、1日空けて明日もう一度やってみる
・毎日の勉強科目に、少しだけ“意図的な混乱”を混ぜてみる
こうしたことを“自分から”始められるなら、成績も記憶力も、間違いなく変わります。
こう言うと、「いや、そこまでやるのはちょっと大変…」と思う方もいるかもしれません。
でも、逆に言えば──
「勉強が苦手なままでいる一番の原因は、“やり方”が間違っているだけ」とも言えます。
才能やセンスの問題ではありません。
正しい方法を、正しい順番で、ほんの少し継続するだけで、誰でも“伸びる側”になれます。
そして、「もっと詳しく知りたい」「この勉強法を深く学びたい」と思った方は、
ぜひ一度、本書『科学的根拠に基づく最高の勉強法』を手に取ってみてください。
難しい専門用語はほとんどなく、どのページも「読む → やってみる」に直結する構成になっています。
あなたの勉強に、きっと新しい視点と結果をもたらしてくれるはずです。
科学的根拠に基づく最高の勉強法amzn.to1,760円(2025年03月28日 16:30時点 詳しくはこちら)Amazon.co.jpで購入する


コメント